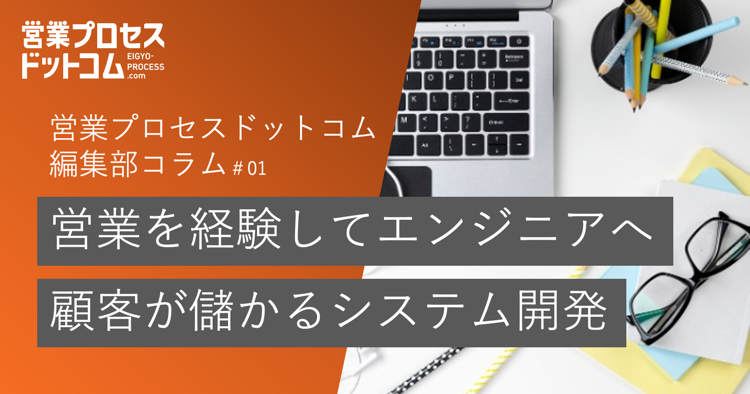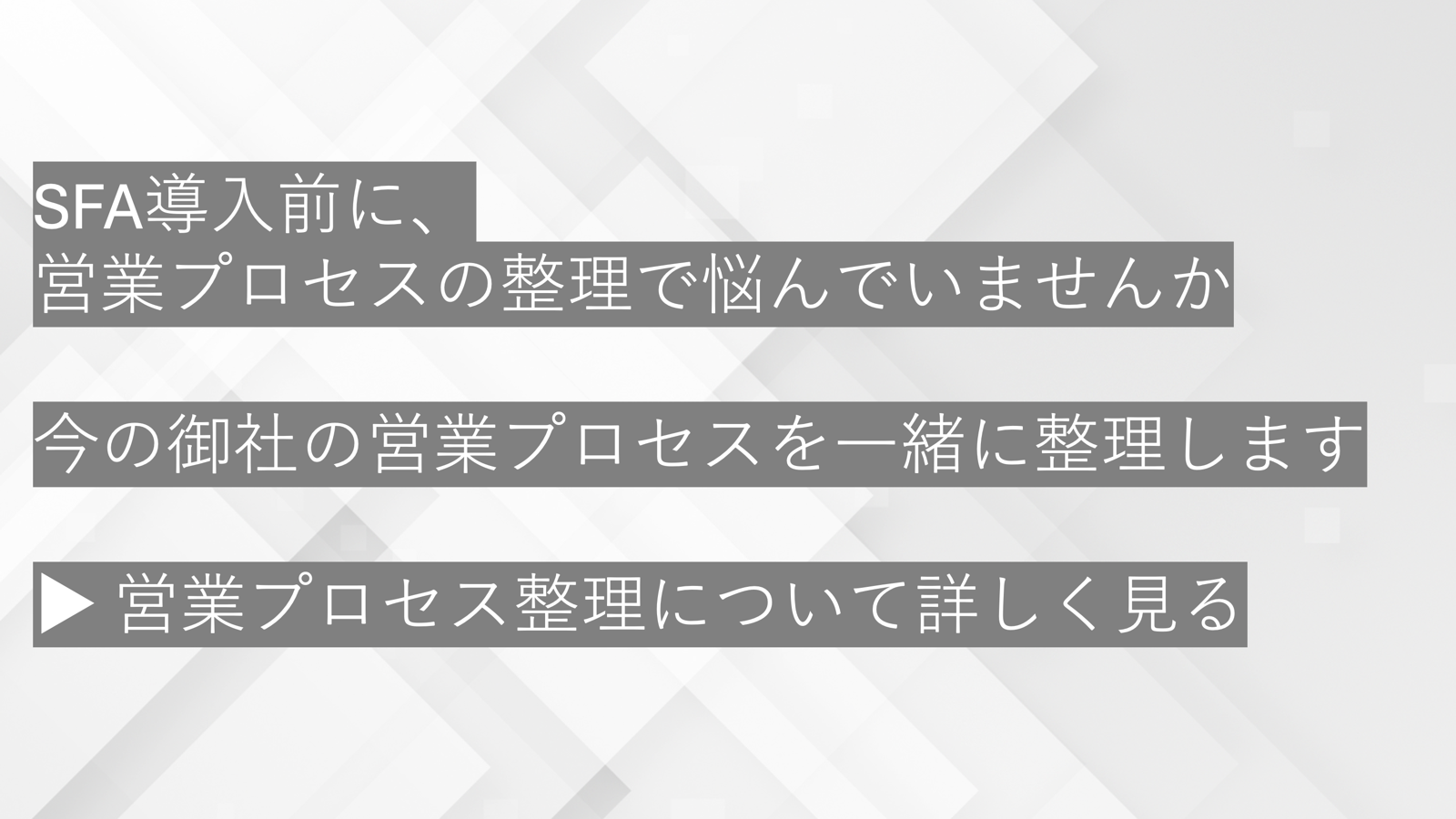私は常に、「営業がわかるエンジニア」でありたいと考えてシステム開発に取り組んでいます。
営業という言葉は「ビジネス」と置き換えても良いかもしれません。
私は営業出身のエンジニアですが、これまで携わってきたシステム開発プロジェクトでは、営業の経験を活かしてプロジェクトを推進してきました。
営業を理解していると、「儲ける」という視点を持って、開発すべき機能のアイデアを提案できるようになります。
システム開発の現場で活きる「儲ける」視点
最近の出来事ですが、私が製品サポート用の生成AIチャットボットを開発したときのことです。
顧客はWeb上で購入できる製品について質問を受け付けるAIチャットボットを構築し、AIが質問者の意図を理解し、応答する仕組みを目指していました。
ユーザーが製品に関する質問をチャットすると、生成AIが内部データをもとに回答文を生成し、チャット上で返信します。
要望を聞いた私は、製品の質問に限定せず購買体験全体を通して質問の回答スピードが上がれば、購買までのリードタイムを短縮し、その分を会計期間中の利益として取り込めると想定しました。
そこで私はユーザーのカスタマージャーニーを作成し、ユーザー接点の創出からアフターサポートまでのコミュニケーションを提案し、顧客に将来的な拡張を提示できました。
生成AIであれば、製品説明を超えて、見積もりの算定理由など細かな質問にも回答できるはずです。
この提案はもっと「儲かる」仕組みにしましょう、ということであり、開発プロジェクトの初期フェーズにおいて、顧客と支援するベンダー双方にとって良い関係づくりに貢献できたと考えています。
「儲ける」視点は営業領域だけではない
「儲ける」という視点は、営業やマーケティングに限らず、あらゆる業務領域に応用できます。
企業の根本的なミッションは利益を上げることにあり、たとえ間接部門であっても、「儲ける」という意識を持って業務にあたれば、会社の利益へ貢献できます。
たとえば、どのような部門であっても経費を削減すれば、その分だけ会社に利益が残るはずです。
現場の担当者が直接的な利益責任を持たない場合でも、会社の誰かがその領域から生み出される「儲け」に責任を負っており、最終的には全体の利益として、社長がその責任を負っています。
「儲ける」視点は会社のどの領域であっても有効なのです。
営業がわかるエンジニアの価値
私は営業がわかるエンジニアはこの「儲ける」視点をシステムに実装できる存在だと考えています。
それは単にザ・モデルや営業戦略、戦術を理解し、SFAやMAツールの開発に役立てているということではありません。
私の場合は「なぜ売上が上がるのか」「どのようにコストを削減できるのか」といった抽象的な問いに意識を向け、仕事に反映できる姿勢を持っているからです。
このメディア「営業プロセスドットコム」という名称は、「営業をプロセスで整理すれば、そこから得られるノウハウ、エッセンスをシステムに反映できる」という視点から名付けました。
今後は、「営業がわかるエンジニア」という少し珍しい立ち位置から、営業ノウハウとシステム開発について発信していきたいと考えます。

ソフトバンクに新卒入社後、法人向けセールスとしてキャリアをスタート。その後は法人マーケティングチームの立ち上げに携わり、ユーザーとしてSalesforceの活用を経験。以降、アビームおよびPwCにてSalesforceを中心としたCRM領域のDXプロジェクトに参画。構想策定から要件定義、開発、実装まで、幅広いフェーズでシステム導入プロジェクトに従事