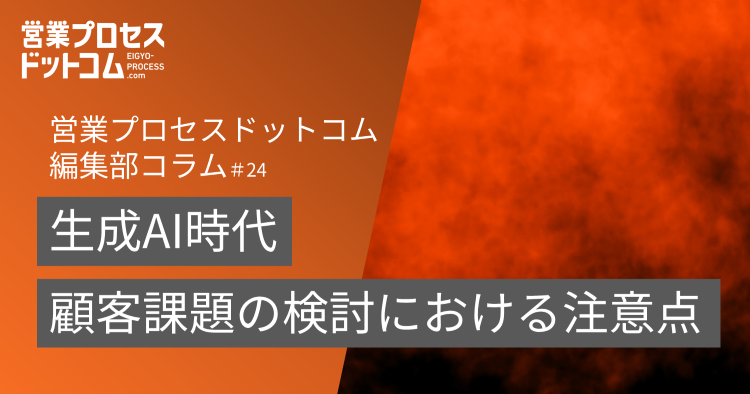顧客に課題を訴求する際、インターネットや業界メディアから「この業界ではこれが課題とされています」といったエビデンスを集め、「これは御社の課題ではないでしょうか」と提示するケースは少なくありません。
しかし、このようなアプローチはあくまで次善策であり、最上の策になりにくいのが実情です。
今回は、なぜ世間一般で語られている課題を提示するアプローチが、あまり有効に機能しないのかについて説明します。
知ったうえで放置されている課題というハードル
まず前提として、ネットやメディアで大々的に語られている業界課題は、顧客側もすでに把握しているケースがほとんどです。
つまり、その課題が顧客にとって
- すでに認識済みで何らかの理由により放置されている
- あるいは、すでに対策を検討・実行済みである
といった状況である可能性が高いのです。
その結果、営業側は「相手がすでに理解している、あるいは真剣に取り組んだ後の課題」に対して、後出しで問題提起を行う構図になりがちです。
この時点で、そのアプローチには大きく二つのネガティブな側面が生じます。
提案価値の不足
顧客がすでに認識している課題に対して、後から情報を集めて提示しても、課題理解の深さや解像度において顧客に劣後してしまいます。
もし顧客が本気でその課題に取り組んでいれば、営業側が考えつく解決策やソリューションは、すでに検討済みである可能性も高いでしょう。
その結果、商談のスタートラインの時点で、顧客にとって新しい価値が何も提示されていない状態になります。
「相手の方が詳しい」「評価される前提がない」という、いわばアウェイな状況から商談が始まるため、主導権を握ることも難しくなります。
「やらない理由」を崩す説得型アプローチ化
すでに顧客がその課題に興味を持っていない、あるいは過去に検討済みのソリューションを提示してしまった場合、商談は次のような構図になりがちです。
「知っているが、やらない」という顧客の現状を、営業が無理に崩そうとする形です。
この状態では、営業はどうしても説得するアプローチに近づいてしまいます。
説得される側の顧客は心を閉ざしやすくなり、こじ開けようとする営業との間に対立構造が生まれやすくなるでしょう。
結果として、商談の流れはスムーズにならず、建設的なコミュニケーションから遠ざかってしまいます。
価値があるのは「相手がまだ気づいていない課題」
営業が課題提起において意識すべきなのは、顧客がまだ気づいていない潜在的な課題を発掘することです。
顧客が意識していない課題には、既存の評価軸や固定観念が存在しません。
そのため、「それは本当に課題なのか」「なぜ起きているのか」を顧客と一緒に考える関係性を築くことができます。
この状態では、営業と顧客は対立関係ではなく、同じ方向を向いたパートナーになります。
生成AI時代は潜在課題に注力すべし
生成AIの普及により、一般論として語られる課題や解決策は、誰でも簡単に手に入る時代になりましたが、その分、「よくある課題」を提示するだけの価値は、急速に薄れています。
だからこそ、課題を提示する際には、
いかに顧客自身がまだ気づいていない重要な課題に気づかせるか
この潜在課題に向けた視点を持つことが、これまで以上に重要になるでしょう。

ソフトバンクに新卒入社後、法人向けセールスとしてキャリアをスタート。その後は法人マーケティングチームの立ち上げに携わり、ユーザーとしてSalesforceの活用を経験。以降、アビームおよびPwCにてSalesforceを中心としたCRM領域のDXプロジェクトに参画。構想策定から要件定義、開発、実装まで、幅広いフェーズでシステム導入プロジェクトに従事